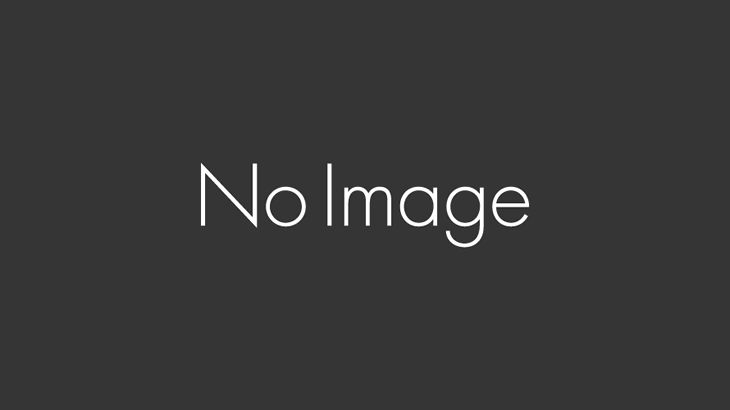- 「水道料金が支払えず止められそう…どうすればいい?」
- 「借金も公共料金も支払えないときの解決方法が知りたい」
家計のやりくりができず、借金返済もままならなくなると、公共料金の支払いさえできなくなります。では公共料金が払えなくなると、どうなってしまうのでしょうか。こちらの記事では公共料金が払えなくなったときに起こること、またその対処法について解説していきます。
公共料金が払えないだけでなく他に借金がある方は、借金返済についても考えなけばなりません。未納分の公共料金とともに、債務整理といった解決方法を模索していく必要があります。注意点やポイントを踏まえたうえで、有効な方法があるかどうか検討していきましょう。
公共料金を払わないとどうなる?
では公共料金を支払わないとどうなってしまうのでしょうか?こちらでは、種類別に起きることについて詳しく解説していきます。
公共料金とは
公共料金とは国や地方自治体といった公的機関が、料金の水準の決定や改定に直接かかわっているものを指します。具体的には次のような料金です。
- 社会保険診療報酬
- 介護報酬
- 電気料金
- 都市ガス料金
- 鉄道運賃
- 乗り合いバス運賃
- 郵便料金
- 電気通信料金
- 公営水道料金
- 公立学校授業料
- 公衆浴場入浴料
こちらの記事では、中でも滞納が問題となりやすい電気料金・ガス料金・公営水道料金について解説していきます。
電気料金
電気料金の構成は、電力会社にかかわらず以下の3種類からなっている場合がほとんどです。
| 基本料金 | 電気の使用料にかかわらず毎月かかる費用 |
| 電力量料金 | 1カ月の使用量と電力単価に応じて金額が変動する |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 電力会社が事業で使用する再生可能エネルギーを買い取った費用の一部を請求したもの |
ガス料金
家庭で使うガスには、比較的料金が安い「都市ガス」と、料金が高めの「プロパンガス」の二種類があります。都市ガスは主に都市部で利用されるタイプのガスで、地中に埋められたガス管を通って、各家庭に供給しています。全国でも数%ほどしか供給ラインが整備されておらず、特に地方では都市ガスが利用できない場合がほとんど。都市ガス料金は、基本料金と使用量に応じて毎月変わる従量料金の二つの要素で構成されています。
一方のプロパンガスは、全国に普及しているもので、ガスボンベで各家庭に供給されていたり、都市ガス同様にガス管を通して供給されていたりします。都市ガスと比較すると価格が高めで、基本料金と従量料金から成る二部料金制となっている世帯がほとんどです。
公共料金に分類されるのは厳密には都市ガス料金のみですが、こちらでは二つの種類を含めたガス料金について見ていきます。
公営水道料金
公共水道料金の請求書を見ると、「水道」「下水道」「基本使用料」の3つから構成されています。基本使用料は、電気代やガス代と同様に、使用水量にかかわらずかかる料金です。そして水道・下水道の項目に関しては、従量料金が採用されていて、使用した量に応じた料金が加算される仕組みです。
基本使用料や従量料金は、お住いの地域によって変わります。また他の公共料金とは違い、2カ月に一度請求される場合がほとんど。他の公共料金よりも、実質的な支払い期間は長いといえます。
【電気料金】滞納した場合
では電気料金を滞納するとどうなるのでしょうか。こちらでは関東を管轄している東京電力の事例をもとに解説していきますが、他の電力会社の対応も基本的には同じです。
延滞利息が発生する
電気料金を滞納すると、遅延損害金が加算されて請求されます。電気料金の支払い期限は検針日の翌日から30日目となっていますが、それを経過しても支払われないと、年利10.0%(一日当たり0.03%)の遅延損害金が加算されることに。遅延損害金の金額は、次の式で算出できます。
例えば電気料金5,000円を50日滞納した場合の遅延損害金は、5,000×10%×50÷365=68.5円となります。貸金業者からの借金の遅延損害金よりは低めですが、使用料が多いケースでは遅延損害金も高額になります。
送電停止の通知が届く
本来の期限までに電気料金の支払いがないときには、電力会社から封書や着圧ハガキで送電停止の通知が届きます。東京電力の場合は、表面に「至急ご確認ください」と印刷されているので、重要書類であることが一目で分かるようになっています。
通知には指定の期日(最終期限日)までに電気料金を支払うように書かれていて、もし支払いがない場合には送電を停止するとの警告文も記載されています。支払方法はコンビニ払いもしくはクレジットカード払いが選択できるようになっているので、通知を受け取ったらすぐに支払うようにしましょう。
送電停止になる
支払期限である検針日の翌日から30日目を過ぎ、20日経過しても支払いが確認できないときには、送電停止の措置が取られます。電気が止められる送電停止の日にちは、最終期限日の翌日以降となっています。最終期限日を過ぎると、いつ電気が止まってもおかしくない状況になります。
こちらは電力会社ごとの支払期限・最終期限日の一覧です。
| 電力会社 | 支払期限 | 最終期限日 |
|---|---|---|
| 東京電力
北海道電力 東北電力 |
検針日(請求日)の翌日から30日目 | 支払期限から20日 |
| 北陸電力 | 検針日(請求日)の翌日から30日目 | 検針日から50日以内
|
| 中部電力
関西電力 中国電力 四国電力 九州電力 沖縄電力 |
検針日(請求日)の翌日から30日目 | 支払期限の翌日から20日目 |
※2024年8月時点の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。
送電停止の後に電気料金を支払った場合、自動的に送電が再開されるわけではありません。電力会社に送電再開の依頼をし、実際に再開されるまでには1~2時間ほどかかります。土日や夜間に送電を停止されるケースはありませんが、依頼のし忘れには注意が必要です。
強制解約される
送電停止されてからもなお滞納を続けていると、10~15日後には電力会社との契約が強制的に解約となります。強制解約になった後で送電を再開してもらうためには、滞納分の支払いにプラスして電力会社との再契約が必要です。契約先が前出の大手10社以外の「新電力」の場合には、再契約を断られる可能性があります。
再契約するには、電力会社のホームページや電話から手続き可能です。ただし今までの電力会社とは違う会社と契約し直す場合でも、滞納していた電気料金は支払う義務があります。
【ガス料金】滞納した場合
ガス料金を滞納した場合は、次のようなことが起こります。こちらでは東京ガスの例をもとに、解説していきます。
延滞利息が発生する
東京ガスの支払期限は、検針日の翌日から30日目です。この期限を過ぎた場合には、一日当たり0.0274%の割合で延滞利息がかかります。電気料金の延滞利息よりも若干低めですが、こちらも支払いを放置しているとガスの供給を停止する旨の通知が届きます。
参考:ガス・電気料金を払い忘れた場合(お支払い期限と延滞利息)|東京ガス
供給停止予告書が届く
支払期限を過ぎても延滞が解消されないと、供給停止予告の通知が届きます。こちらの通知には、請求の対象となる月と料金、最終支払期限、そして支払わなかった場合のガス供給が止まる日にちについて記載されています。都市ガスの供給停止日は、検針日翌日から50~60日後、支払期限から20~30日後です。
供給停止になる
供給停止予告の通知に記載された日付を過ぎても料金の支払いがない場合には、ガスの供給が停止されます。停止される直前の通知はなく、供給停止後に「供給停止のお知らせ」という報告書が送付されます。
こちらも供給を再開するためには、滞納分をすべて支払わないといけません。供給停止の通知に添付されている振込用紙を使って、コンビニやガス会社の事務所で支払ってください。
【水道料金】滞納した場合
水道料金を滞納した場合にも最終的に給水停止となります。水道料金は上水道と下水道の二種類で構成されていて、一般的に水道料金といわれるのは上水道料金です。水道料金の延滞は、電気やガスと比較すると次のような点が異なります。
- 延滞利息がかからないことがある
- 給水停止までの期間が長い
- 滞納が長いと督促の電話や訪問が行われる場合がある
こちらでは、滞納から給水停止までの流れを詳しく解説していきます。
遅延損害金が発生する
電気やガス料金と同様、水道料金を延滞すると遅延損害金がかかります。自治体によっては上水道料金については「遅延損害金」、下水道料金については「延滞金」としています。さらに自治体ごとに遅延損害金がなかったり、利率がバラバラだったりします。
多くの自治体では民法第404条に規定されている法定利率の年利3.0%を採用しています。まずはお住いの自治体が設定している遅延損害金についてチェックしましょう。
督促状が届く
水道料金の支払期限は、通常請求書が発行されてから10日です。この期限から1カ月ほど経過すると、「督促状(催促状)」が届きます。書面には水道料金の支払いが確認できない旨と請求金額、支払期限やコンビニ納付用のバーコードが記載されています。口座振替で納付する場合には、口座振替請求書が督促状の代わりとなります。
自治体によっては、督促状の送付後にさらに「勧告書」を送付するところもあります。他にも電話での連絡や使用場所への訪問を行う自治体もあるので注意してください。
給水停止予告書が届く
本来の支払い期限から2カ月過ぎると、「給水停止予告書(給水停止執行通知書)」が送付されます。この通知書が発送される条件は自治体によって異なりますが、以下の内容が記載されている場合が多いです。
期日までに支払いがない場合、指定した日に給水停止する
給水停止しても支払いがない場合、裁判所へ申立てをする
これまでの督促状や催告書よりも、内容は厳しいものとなっています。
給水停止通知書が届き、水道が止まる
前出の給水停止予告書の日付けが過ぎると、水道局の担当者が来て水道の元栓を閉めます。止める直前の予告はなく、元栓を閉めた後に「給水停止通知書」を家に置いていきます。現地に直接止めに来るため、水道が止まるのは平日の日中です。
クレジットカード払いにしている人はブラックリストに登録される
公共料金の支払いをクレジットカード払いにしている方は、その情報が個人信用情報に登録されます。いわゆる「ブラックリスト状態」です。ブラックリスト状態になると次のようなことができなくなります。
- ローンやキャッシングができない
- クレジットカードの利用・新規契約・更新ができない
- 携帯電話本体の分割払いができない
- 奨学金等の保証人になれない
- 信販系の保証会社との契約が必須な賃貸物件が借りられない
クレジットカードの利用料金を2~3カ月支払わなかった場合、その内容にかかわらず個人信用情報に登録されます。ブラックリスト状態が解消されるまでの期間は、信用情報機関によって異なるものの、完済から5年程度となっています。
ブラックリスト登録期間や消し方については、こちらの記事を参考にしてください。
「ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法」
公共料金を滞納した後の対処法
公共料金を滞納した場合、次のような対処をしていきましょう。
滞納分の全額を支払い再開の手続きをする
すでに送電・供給・給水停止となっている場合には、滞納している公共料金を全額支払い、事業者に連絡することでまた使えるようになります。
【電気】
電力会社への連絡から送電が再開されるまでの時間は、地域によって異なるものの、ほとんどのケースで1時間以内に再開されます。自宅に備え付けられている電力量計にスマートメーターが搭載されている場合には、遠隔操作で24時間いつでも再開可能です。
スマートメーターがない場合には、作業員による通電再開の工事が必要です。支払の連絡が夜間の場合には、送電再開は翌日の9時以降になる可能性があります
【ガス】
滞納しているガス料金を支払った後の供給再開の連絡は、ガス会社の受付時間内にしなければなりません。東京ガスの場合は、インターネットで24時間受付可能ですが、16時半(日祝日は14時半)以降の連絡は、翌日9時以降の対応となります。
ガスの供給再開には、利用者の立ち合いが必須なことが多いです。そのため、なるべく早めに支払い後、連絡するようにしましょう。
【水道】
延滞している水道料金については、水道局の窓口で支払えば、早いと当日のうちに給水を再開してもらえます。水は人の命にかかわる上に自治体が管轄しているので、他の公共料金と違って支払方法についても融通を聞かせてもらえる可能性が高いです。支払えないかもしれないというときには、早めに相談するようにしましょう。
保証金を支払う
送電を再開するタイミングで、保証金の支払いを要求される場合があります。保証金とは今後電気料金を滞納したときに、料金の支払いに充当するためのものです。保証金の金額は電力会社によって異なるものの、予想月額料金の3カ月分程度という場合が多いです。
東京電力の約款では、現在電気料金を滞納している人の他、過去に滞納の実績がある人なども保証金を請求される可能性があります。
電気は1アンペア契約に切り替える
電気料金の滞納が続くと最終的に送電停止となりますが、事前に1アンペア契約に切り替えておくと、送電停止の事態を避けられるかもしれません。1アンペア契約とは、最も低い電力供給の契約形態で、主に一人暮らしのアパートや非常に少ない電気の使用で済む家庭で契約されています。
電力会社によっては、1アンペア契約をしている利用者に対して、送電停止の基準を緩やかに設定しているため、通常の契約よりも送電停止までの期間が延ばせる可能性があります。とはいえ1アンペア契約でも、滞納が続くと最終的には送電停止となります。いずれの場合でも滞納が発生したときには、速やかな対応を心がけてください。
事業者に相談する
料金をすでに滞納している、今後滞納しそうというときには、事業者に相談することをおすすめします。場合によっては支払い猶予や分割払いに応じてくれる可能性があります。
とくに近年、新形コロナウイルスの影響によって、公共料金の支払いができなくなっている人が増えています。そのため経済産業省では、各事業者に対して利用者の状況に応じて支払いを猶予するようにとの要請を出しています。要請を受けて各事業者では、支払に困ったときは相談するようにと利用者に呼び掛けています。
供給停止の延期を依頼する
水道料金の納付期限前に水道局に連絡すると、供給停止の延期ができる場合があります。水は生命に欠かせないもので、自治体が管理しているため融通が利きやすいです。延期を受け入れてもらえないケースもありますが、実際に受け入れてもらえたという人も少なからずいます。何もせずに供給停止になるよりは、可能性にかけてみた方がいいでしょう。
支払期限の延長
電気事業者によっては、支払期限の延長が可能な場合があります。延長できる期間は1~2カ月ほどです。
インターネット上から延長の申し込みができる場合もあるので、一度調べてみてはいかがでしょうか。
分割払いをお願いする
自治体によっては、水道料金を分割で支払えるところがあります。場合によっては誓約書や納入計画書の作成が必要ですが、滞納分を一括で支払えない方は相談してみましょう。
ただし分割払いになったにもかかわらず滞納を繰り返す人に対しては、以後支払期限の延長や分割払いが認められなくなります。同時に滞納分を全額納付しない限りは給水を再開しないといった厳しい措置が取られる可能性があります。
使用量・利用プランの見直し
事業者に連絡すると、電気やガスの使用量、料金プランの見直しをアドバイスしてもらえる場合があります。例えば使用量が少ない家庭では、基本料金が安いプランに変更するなどです。また毎月の水道料金を削減するために、節水や利用料の見直しの提案を受けられる場合があります。
サポート制度・支援制度の紹介
電気事業者やガス事業者の中には、経済的困難を抱えた人のためのサポート制度や支援制度を設けているところがあります。無料相談窓口を通したアドバイスや、料金負担軽減のための支援が受けられる場合も。過去には電気料金や都市ガス料金が使用料に応じて自動的に割引される制度もありました。
支払に優先順位をつける
複数の公共料金を滞納していてすべての支払いが難しい方は、支払に優先順位をつけるといいでしょう。とくに水道は給水停止までの期間が長く、自治体によっては分割払いは支払期限の延長に応じてくれるところも。前もって水道料金の支払いについて相談し、電気やガスの料金を優先して支払うといいでしょう。
また生命維持のためにエアコンの使用が欠かせない夏は電気料金の支払いを最優先にする、飲み水確保のために水道料金を次に支払うなど、ケースごとに優先順位をつける方法もあります。とはいえ、全ての料金の延滞は最終的に解消しなければなりません。
滞納分のお金を工面する
滞納分のお金を、何とか工面するという方法もおすすめです。具体的には次のような手段でお金を作りましょう。
- 家族や友人に借りる
- 不用品を売る
- 副業やアルバイトで収入を増やす
- 支出を見直し固定費を削減
早急に滞納を解消するには、家族や親族にお金を借りる、不用品を売る方法が手っ取り早いです。長期的な視点で見ると、副業や支出の見直しが有効です。
病気で借金が返せないときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「病気で借金が返せない!今すぐやるべきことから借金問題解決までを一挙解説」
公的支援制度を利用する
失業などで収入が途絶えたり、病気やケガで働けないときには、公的支援制度を利用して公共料金の支払いに回す方法があります。
| 支援制度の種類 | 要件・条件 | 金額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 失業手当 | 失業状態であること
ハローワークに求職の申し込みをするなど転職活動をしていること 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること |
基本日当額=賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%) | 現住所を管轄するハローワーク |
| 総合支援資金(生活福祉資金) | 低所得者世帯または住居確保給付金申請者
失業など日常生活全般に困難を抱え、生活再建のために生活費や一時的な資金を必要としている 貸付により自立が見込まれる世帯 |
生活支援資金:1世帯当たり最大20万円
住宅支援資金:1世帯当たり最大40万円 一時生活再建資金:一世帯当たり最大60万円 |
お住いの地域の市区町村社会福祉協議会 |
| 緊急小口資金(生活福祉資金) | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯 | 一世帯当たり最大20万円 | お住いの地域の市区町村社会福祉協議会 |
| 住居確保給付金(生活福祉資金) | 同世帯の方の死亡、離職、休業等により住居を喪失またはその恐れのある人
世帯収入が著しく減少した月から2年以内 世帯収入額・金融資産の合計が一定額以下である |
世帯の人数により12万~20万円程度 | お住いの地域の自立相談支援機関 |
| 生活保護 | 世帯員全員が資産能力その他あらゆるものを生活維持のために活用すること
親族等から支援を受けられないこと 厚生労働大臣が定める最低生活費よりも世帯収入が少ない場合 |
世帯人数やお住いの地域により異なる | お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当 |
お金がなく困ったときに利用できる公的救済制度については、こちらの記事を参考にしましょう。
「お金がない…助けて!原因やNGを知って公的救済制度・状況別対処法で乗り切ろう」
債務整理を検討する
公共料金の支払いが滞る程に収入が減った場合や、借金があって公共料金を支払うことができない場合には、債務整理を検討しましょう。債務整理には主に次の3種類があり、手続きの方法や減免割合が異なります。
任意整理
任意整理とは、債権者と直接交渉して将来利息や遅延損害金を減額してもらう手続き。残った借金は3年~5年かけて完済を目指します。ただし公共料金の場合、そもそも利息がかからず延滞料金は交渉しても免除されることはありません。そのため任意整理をしても、公共料金の延滞は解消されないことを覚えておきましょう。
とはいえ公共料金の延滞以外にキャッシングやローンの滞納がある場合には、金利の高い借金を減額し返済期間を延長することで毎月の負担が軽減できます。浮いたお金で公共料金の延滞を解消でき、以後はきちんと支払っていけるようになることが期待できます。
任意整理で減額されない理由や原因は、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」
個人再生
個人再生とは、裁判所に再生計画案を認可してもらうことで、借金を大幅に減額できる手続き。公共料金の滞納に関しても申立て可能ですが、再生手続開始前6カ月分の滞納は、個人再生しても減額できません。というのも民法では、公共料金を「日用品供給の先取特権」として再生手続によらず随時弁済するものとしています。
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
(日用品供給の先取特権)
第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
引用:民法|e-GOV法令検索
個人再生の必要書類と流れが知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生の流れと必要書類とは?手続きにかかる期間と書類の入手方法も解説!」
自己破産
自己破産とは、返済不能状態を裁判所に認めてもらうことで、すべての借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続き。公共料金の滞納や破産手続開始前までに発生した公共料金についても自己破産の対象となりますが、破産手続開始決定後に発生した公共料金の支払い義務は対象外となるため、随時支払っていく必要があります。
自己破産は自分で手続きができるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産は自分でできる?手順と注意点、弁護士に依頼しないときのデメリットとは」
公共料金の滞納に関する注意点
公共料金の滞納があった場合や、債務整理を検討しているときには、次のような点に注意してください。
下水道料金は債務整理しても減免できない
公共料金の滞納に関しては個人再生や自己破産で減免可能ですが、下水道料金のみ債務整理しても減免できません。というのも下水道料金は自己破産しても免責されない「非免責債権」に該当するためです。下水道料金は他の公共料金と異なり、自治体による強制徴収が認められています。
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
これによって下水道料金は「租税等の請求権」に準じた扱いになり、破産法第253条に定められている非免責債権となります。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
自己破産ができないケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産ができない9つのケースとは?対処方法や自己破産に適さない人について解説」
公共料金の滞納の時効について
借金の請求権には時効がありますが、公共料金にも時効が存在します。
| 電気料金 | (2020年3月31以前契約分) 2年
(2020年4月1日以降契約分) 5年 |
| ガス料金 | (2020年3月31以前契約分) 2年
(2020年4月1日以降契約分) 5年 |
| 水道料金 | 上水道料金 (2020年3月31以前契約分) 2年
(2020年4月1日以降契約分) 5年 下水道料金 5年 |
電気・ガス・上水道料金は、契約時期によって2年~5年の時効となります。一方で下水道料金は契約時期の如何にかかわらず、地方自治法第236条によって5年で時効外成立するとしています。
時効を有効にするには「時効援用」という手続きが必要です。具体的には事業者に対して「時効援用通知書」を送付することで法的な支払い義務がなくなりますが、時効援用には専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談、依頼することをおすすめします。
時効援用の方法と時効の実態については、こちらの記事を参考にしましょう。
「10年放置した借金は時効で返済義務がなくなる?時効の実態と援用について解説」
公共料金を滞納してもやってはいけないこと
公共料金を滞納していても、次のような行為はNGです。
督促や催促を無視する
督促や催促を無視するのは、公共料金でなくてもNGです。最悪の場合、裁判所に差押えの訴訟をされ、強制執行を受ける恐れがあるため。給与を差し押さえられれば、勤務先に公共料金を滞納していたことがバレてしまいます。また預貯金の差し押さえを受けると、口座にあるお金が引き出せなくなり生活に影響が出るケースも。
差し押さえを免れるために財産隠しをすると、刑事罰の対象となる可能性があります。延滞して督促や催促の連絡が入ったときには、内容を確認したうえで速やかに対応してください。
金利の高い業者から借りて支払う
公共料金の支払いができずに困っていたとしても、金利の高い貸金業者などから借りて支払うのはおすすめできません。一時的に対応できたとしても、結局は新たに借りた借金を返さなければなりません。返済目途が立たない状態で安易に借りてしまうと、新たな滞納を発生させる原因に。
貸金業者からの借金には低くない利息が付きます。借金を返すためにまた別のところから借りて…を繰り返していると、あっという間に借金が増えてしまいます。このような状態になる前に、他の方法で対処していきましょう。
違法な業者から借りて支払う
借金を繰り返していると、やがて正規の貸金業者から借入ができなくなります。貸金業法には借り過ぎによる多重債務を防ぐための「総量規制」があり、個人の場合には年収の1/3までしか借入ができません。また返済ができず一定期間延滞するとブラックリストに載り、それによっても新たな借入ができなくなります。
このような中、「だれても借りられます」「ブラックでもOK」という貸金業者がいます。しかし安易にこのような業者に手を出してしまうと、高すぎる金利を請求されたり、厳しい取り立てを受けるなどトラブルに見舞われる可能性が高いです。このような違法な業者は「闇金」や「ソフト闇金」と呼ばれています。
滞納していてお金に困っていたとしても、違法な業者とはかかわらないようにしてください。
ソフト闇金と闇金の違い、よくある手口については、こちらの記事を参考にしましょう。
「ソフト闇金と闇金の違いって?よくある手口と見分け方、知らずに借りたときの対処法とは」
クレジットカードのショッピング枠の現金化
ネットの情報などを見て、クレジットカードで高価な商品や金券を購入し、金券ショップや質店などに売却すればお金が手に入ると考える人もいます。しかしこれは誤ったクレジットカードの使い方で、カード会社の規約に違反する行為です。
後日カードの請求を受けるだけでなく、カード会社からペナルティを受ける可能性も。滞納があったとしても、間違った方法で現金を用意しようとしてはいけません。
クレジットカードの一括請求を無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなる?主な流れと解決方法を紹介!」
まとめ
電気・ガス・水道などの公共料金が払えないと、延滞利息が発生し、書面等で督促を受けます。それでも放置していると最終的には供給を止められてしまうでしょう。供給停止を解除するには滞納分を支払い、事業者に連絡することが必須です。
滞納が発生したら事業者に連絡し、分割払いや支払期限の延長ができないか相談しましょう。支払先に優先順位をつけ、様々な方法でお金を作るのもおすすめです。事業者が案内する支援制度や公的貸付制度、生活保護などの利用も検討したうえで、他の借金がある場合には債務整理を検討してください。
任意整理では公共料金の減額はできません。個人再生では再生手続開始前6カ月分の滞納は手続きの対象外です。自己破産では下水道料金が免責できないので注意が必要です。債務整理を検討した場合は、自分にあった方法をアドバイスしてもらうためにも、借金問題に詳しい弁護士に相談しましょう。