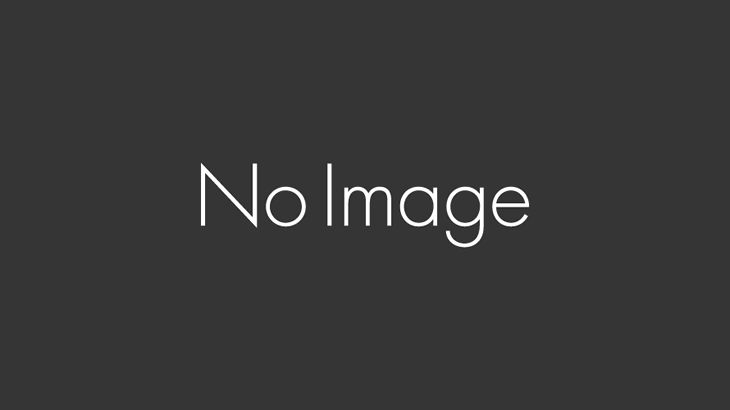- 「住民税を払わずに放置していると、最終的にどうなるの?」
- 「税金を含む借金問題を解決する方法が知りたい」
会社員なら原則として給料から天引きされる住民税ですが、天引きされない会社に勤めているかたや個人事業主の場合は、自分で納税しなければなりません。そのためつい納付期限を過ぎてしまったというケースも少なくありません。では住民税を滞納し続けると、どのようなことが起きるのでしょうか。
こちらの記事では住民税を滞納するリスクやその理由、滞納後の流れについて詳しく解説。さらに税金以外の借金の解決方法についても相談するので、税金以外に滞納している借金もあるという方は参考にしてください。
住民税の滞納と時効について
では、住民税の滞納はどのような理由から起こるのでしょうか。「滞納し続けていてもいずれ時効が来れば払わなくてもよくなる」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。このようなうわさが本当なのかも併せて解説していきます。
住民税とは
住民税とは、都道府県や市区町村といった自治体が住民に提供する行政サービスのために徴収する税金のこと。「市区町村民税(市町村民税・特別区民税)」と「都道府県税」の2つから構成される地方税です。前年の所得をもとにして計算され、その年の1月1日時点で住所がある自治体に対して支払います。
給与所得者(会社員)でも事業所得者(個人事業者)でも課税方法は同じですが、納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
住民税の金額の決め方
住民税の金額は、前年1月1日から12月31日までの収入によって決定されます。退職して収入が無い人も、転職して収入が減少した人でも、前年の収入を基にして計算された住民税を支払わなければなりません。実際の住民税の金額は、毎年5~6月頃に勤務先に届く「住民税決定通知書」を見ると分かります。
ちなみに住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず一定額の負担を求める「均等割」の二種類があります。所得割の税率は、市町村民税が6%、道府県民税が4%の合計10%となります。
均等割の対象となるのは、未成年者・障害者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、かつ合計所得が135万円以下であることが条件です。このような人以外は所得割で計算されます。
住民税の滞納が起きやすい理由
上で少し触れましたが、住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収の」2種類があり、この2つの納付方法があることで住民税の滞納が起きやすくなっています。それぞれの納付方法の違いは以下の通りです。
| 普通徴収 |
|
| 特別徴収 |
|
普通徴収による滞納
事業所得者は普通徴収になるので、自分で金融機関の窓口などで住民税を納付しなければなりません。あらかじめ口座振替に設定している方以外は、納付忘れや延滞の可能性があります。また納付期限が毎月ではなく年4回というのも、納付忘れになりがちな理由です。
一括納付で1年分をまとめて納付するという方法もありますが、金額負担が多くなることから多くの人は分割納付を選択します。このようなことから、普通徴収による滞納が発生します。
特別徴収→普通徴収に変更したことによる滞納
納付忘れが起きるもう一つの理由が、徴収方法が変わったことによるものです。今までは特別徴収で勝手に給与から天引きされていたものが、退職によって普通徴収に変わったり特別徴収に対応していない会社に転職したりすると、自分で住民税を納めなければなりません。
徴収方法が変わったことに気が付かないと、うっかり納付忘れという事態に。退職や転職をした場合には、住民税の支払いがどうなるか忘れずに確認するようにしましょう。
時効が来れば納税しなくてもいい?
税金の納付にも時効があり、時効が来れば払わなくてもいいのでは?と考える人がいるかもしれません。確かに地方税は納付期限の翌日から起算して5年で時効が成立し、その支払い義務は消滅します(地方税法第18条)。しかし役所は税金が支払われていないまま放置することはありません。
滞納してしばらくすると、役所から督促や催告状が届きます。このような通知により時効が中断(更新)され、また1からのカウントになります。そして5年を経過することなく税務署から差し押さえの連絡が届きます。住民税の時効を期待するのは無駄なこととして、別の方法での解決を検討すべきでしょう。
借金の時効援用が失敗するケースについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」
債務整理しても税金はなくならない
借金問題を解決する方法として「債務整理」があります。しかし税金は、債務整理による減額や免除の対象外です。このような借金のことを「非免責債権」といい、税金の他にも次のようなものが該当します。
- 租税等の請求権(税金・社会保険料・国民健康保険料・下水道料金など)
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重大な過失による人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 不法義務に基づく金銭債務(養育費・婚姻費用など)
- 罰金・過料・科料など
債務整理するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理したらどうなる?デメリットや影響を把握して、後悔しない借金解決方法を!」
住民税を滞納する5つのリスク
では住民税を滞納するとどのようなリスクが発生するのでしょうか。
延滞税が発生する
住民税を滞納するすると、滞納が解消されるまで「延滞税」が発生します。滞納期間が長くなればなるほど延滞税が加算されるので、その税負担は大きくなるばかりです。ちなみに延滞税の金額は、次の計算式で算出できます。
上記の「延滞税率」は、納付期限の翌日からどのくらいの期間滞納しているかによって変わってきます。
| 納期限翌日から2カ月経過する日までの滞納 | 年7.3%または「延滞税特例基準割合(2.4%)+1%」のうち低い方 |
| 納付期限翌日から2カ月を経過する日の翌日以降の延滞 | 年14.6%または「延滞税特例基準割合(8.7%)+7.3%」のうち低い方 |
参考:延滞税の割合|国税庁
ちなみに事業所得者の場合は自分で確定申告の必要がありますが、確定申告の期限を過ぎた場合にも延滞税が発生します。また確定申告の内容を間違えて少なく申告した場合にも、税金を滞納したと判断されて延滞税が加算されるので注意が必要です。
督促状・催告書が自宅に届く
住民税を滞納すると、納付期限から20日以内に役所から「督促状」が届きます。それでも納付しないでいると「催告書」が何通も届くように。督促状や催告書には法的な強制力がないものの、自宅に届くので家族に住民税を滞納していることがバレてしまうかもしれません。
これらの文書には、次のような内容が記載されています。
- 税金の種類・期別
- 本来の納付期限
- 納付税額
- 延滞税の金額
- 納付書の取扱期限
督促状に記載されている延滞税の金額は、記載日現在のものなので、実際に払う場合にはその日で計算し直す必要があります。また督促状に同封されている納付書には取扱期限があり、その期限を過ぎると使用できなくなるので注意しましょう。
財産が差し押さえられる
督促状発行から10日経っても滞納が解消されないときには、自治体は滞納者の財産を差し押さえできるようになります。金融機関からの借金を延滞した場合には、債権者が裁判所に申し立てて差し押さえが認められて初めて強制執行が可能になります。
しかし税金など債権者が役所の場合には、裁判手続きが必要ありません。督促状を無視し続けていると、ある日突然給与や預貯金が差し押さえられる可能性があります。
勤務先にバレる
給与所得者の場合、住民性を滞納すると真っ先に給与が差し押さえの対象となります。役所から勤務先に差し押さえる旨の通知が届くため、会社に税金を滞納していることがバレてしまいます。そうなるとあなたの社会的信用を失うリスクがあるでしょう。
自営業者は資金繰りが悪化する
自営業者の場合、差押えによって預金口座が対象となると新たに銀行から融資を受けるのが難しくなり、結果的に資金繰りが悪化する恐れがあります。また取引先に税金を滞納したことを知られてしまうと、信用を失って仕事まで失ってしまう可能性があります。
預貯金以外の事業資産(不動産・車・機械・船舶・器具工具備品など)も差し押さえの対象になると、事業自体を続けることができなくなります。自営業者にとっても、住民税の滞納はリスクしかありません。
法人破産で代表者はどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「法人破産で代表者どうなる?本人と周囲への影響、リスクを最小限にする方法を解説」
住民税滞納から差し押さえまでの流れ
では住民税を滞納した場合、どのような流れで差し押さえになるのでしょうか。
督促状が届く
前出の通り、住民税を滞納すると納付期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状の送付は、地方税法で定められた手順なので、必ず実施されます。
第三百二十九条 納税者(中略)が納期限(中略)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。(以下略)
催告書・差押予告書が届く
督促状が届いてそれでも住民税を納付しないでいると、届く文書が催告書や差押予告通知書といった名称に変わります。目立つように派手な色の封筒に入っていたり、内容証明郵便で届く場合があります。これらの文書は差押え前の最終勧告であることを伝えるものです。
地方税法では、督促状を発送した日から10日を経過日までに滞納が解消されないと、差押えが可能としています。
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。(以下略)
かし実際には、役所では催告書や差押予告通知書を送付して、できる限り差し押さえは行わずに任意での納付を促す配慮をしています。お住いの地域によって対応が異なるものの、差押予告通知書は滞納から数カ月後になることが多いです。このような文書が届いたときには、無視せず対応するようにしましょう。
財産調査の実施
差し押さえが必要と役所が判断した場合には、財産調査が行われます。刑事事件の家宅捜索に似たような形で、実際に自宅や職場に立ち入られて、差し押さえできる財産がないかや隠し財産を持っていないか調査されます。また役所は、滞納者と取引関係のある第三者に対する調査も可能です。勤務先はもちろん、家族や取引先にも連絡がいく可能性があります。
調査を受ける先の人や関係する金融機関は、役所の財産調査に協力しなければなりません。住民税の滞納がこの段階で周囲に知られる可能性が高いでしょう。
差し押さえ処分
財産調査で差し押さえできる財産が見つかったときには、実際に差し押さえ処分が実施されます。役所の差し押さえにおいては、裁判所の判断や滞納者の同意は不要です。ある日突然次のようなものが差し押さえになる可能性があります。
- 給与
- 預貯金
- 不動産
- 事業資産
- 動産(現金・家財道具・車など)
住民税の滞納で差し押さえられるまでの流れについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「住民税の滞納で差し押さえられるまで|滞納リスクと流れを理解し、差し押さえを回避」
給与の差し押さえ額
給与所得者の場合、真っ先に給与が差し押さえの対象となります。ただし全額を差し押さえしてしまうと、滞納者の生活が立ち行かなくなってしまいます。そのため役所では1カ月の支給額の1/4相当額を差し押さえの上限額としています。
詳しく計算すると、給与の額面金額から次のようなものを指しい引いた金額となります。
- 所得税・住民税・社会保険料の控除分(1,000円未満切り上げ)
- 10万円
- (扶養家族がいる場合)1人につき45,000円
- 額面金額から1~3を引いた金額の20%
給料差し押さえは無視できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」
預貯金の差し押さえ額
給与と違い、預貯金には差し押さえの上限額は決められていません。そのため滞納している住民税の金額分が口座にある場合には、全て差し押さえの対象となります。預貯金を差し押さえられると住民税の納付分が口座引き落としとなり、通帳には「サシオサエ」「ジュウミンゼイサシオサエ」などと記載されます。
完納するまで差し押さえが続く
一度給与や預貯金が差し押さえの対象となると、原則として未納分を完納するまで差し押さえは解除されません。給与が差し押さえの対象となった場合には、返済分が差し引かれた給与が口座に振り込まれます。また預貯金が差し押さえとなった場合には、完納するまで複数回口座から引き落としされます。
ただし差し押さえによって生活が苦しくなるときには、生活保護の受給や「換価の猶予」申請によって差し押さえを解除できる場合があります。詳しくは次の項目で解説します。
住民税を滞納した場合の対処法
住民税を滞納すると、最悪の場合給与や預貯金が差し押さえとなります。そうならないために、早めに適切な対処をしていきましょう。
すぐに支払う
手元にあるお金で滞納分を支払えるときには、すぐに納付手続きをとりましょう。督促状などに同封されている納付書を使って、銀行の窓口やコンビニで支払ってください。納付するときには、新しく届いた督促状についている、取扱期限内の納付書を使ってください。
役所に相談する
督促状などに記載されている期限まで支払えそうもないときには、役所の住民税担当部署の窓口に相談してください。支払う意思があるときには、今後の納付方法や納付計画について相談に乗ってもらえます。その際には督促状を受け取った日からではなく、発送された日付から10日以内に相談に行くようにしましょう。
すぐに支払うことができない事情を正直に話したうえで、それでも納税の意思があることを伝えれば、いきなり差し押さえを受けることはありません。
減免申請をする
一定の要件を満たす場合には、住民税を減免してもらえる可能性があります。自治体の規定によって異なる部分もありますが、一般的には次のような要件を満たすと減免が受けられます。
- 生活保護を受給中
- 解雇や廃業によって失業中
- 災害により大きな損害を受けた
- 障害者認定を受けている
- 勤労学生である
他にも前年の所得合計が一定以下の人や、均等割りの対象となる人が該当する可能性があります。詳しくはお住いの自治体役場にお問い合わせください。
病気で借金が返せないときの解決方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「病気で借金が返せない!今すぐやるべきことから借金問題解決までを一挙解説」
納税猶予(分割納付・延納)申請をする
減免してもらうのは難しい場合でも、分納による納付や延納などが可能な場合があります。お住いの自治体によって細かく要件が規定されていますが、納付困難と認められれば1年程度の納付猶予に対応してもらえる場合があります。納付猶予が認められる可能性があるのは、次のようなケースです。
- 本人や家族の病気・怪我
- 廃業や休業
- 災害や盗難などの被害にあった
- 事業上の著しい損失が発生した
自営業で借金返済が苦しいときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「自営業で借金返済が苦しい。会社の事業継続・廃業それぞれに向けたベストな対処法とは」
換価の猶予申請をする
住民税の滞納によってすでに差し押さえを受けている場合でも、生活の維持が難しいと判断されると差し押さえを待ってもらえる制度があります。これを「換価の猶予」といいます。すでに不動産などの差し押さえが決定している場合でも、換価の猶予申請をすれば換価処分(公売)を待ってもらえます。
また換価の猶予申請が認められると、猶予期間中の延滞税についても一部または全部が免除されます。差し押さえされると生活できないという場合には、早めに役所に換価の猶予申請を行ってください。
延滞税の軽減制度
住民税の滞納によって延滞税が加算されている場合、延滞税の軽減制度が受けられる可能性があります。こちらは確定申告をした人限定の特例ですが、次のようなケースが該当します。
- 期限内に確定申告をしたが、申告期限から1年経過してから修正申告または更正があった
- 申告期限に遅れて確定申告したが、申告後1年経過してから修正申告または更正があった
これら2つのケースでは、一定期間の延滞税を加算しないという特例措置が取られます。これは税務調査の時期が税務署の都合で左右されるため、納税者にかかる延滞税の負担を不公平にしないための措置です。
生活保護の受給
生活に困って住民税が支払えないときには、生活保護の受給を検討しましょう。生活保護制度は憲法に定められている「健康で文化的な最低限の生活を保障する」ためのものです。保護費は税金から支給され、生活保護受給者は、原則として非課税となります。
すでに差し押さえを受けている場合には、差し押さえが解除(滞納処分の執行停止)となります。そして生活保護を受給して3年が経過しても、経済状況に大きな改善が見られなければ、処分が停止されていた滞納分は取り消しとなります。ただし生活保護を受給するには、次のような要件(基準)を満たさなければなりません。
- 世帯収入が最低生活費に満たない
- 病気などやむを得ない理由で働けない
- 身内に経済的援助をしてくれる人がいない
- 資産を持っていない
- 生活保護以外の公的支援が受けられない
借金で首が回らないときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金で首が回らない…どうすれば?完済のための8つの対策を知り、債務整理が可能か判断しよう」
税金以外の借金を解決するには…債務整理を検討
住民税を滞納している方の中には、返済できない程の借金を抱えている方が少なくありません。また借金を減額できれば、住民税の滞納を解消できるという人もいるかもしれません。そのような場合には、税金以外の借金を債務整理することをおすすめします。
債務整理には次の3つの方法があり、それぞれで手続き方法や減免割合、条件などが異なります。
任意整理
任意整理とは、貸金業者と直接交渉することで、将来利息や遅延損害金を減額してもらう手続き。減額後は3年もしくは5年かけて返済していきます。2008年以前からの借金を今も返済し続けている方は、過払い金が発生しているかもチェックしましょう。
任意整理は手続きする債権者を選べるので、保証人がいる借金や車のローン、住宅ローンなどを手続きから外すことができます。また勤務先や家族に知られにくいのも、任意整理のメリット。すでに借金を相当期間滞納している方や、リボ払いのような高い利息の借金を抱えている方に向いています。ただし手続き後も返済が続くため、安定した収入が無いと債権者が交渉に応じてくれない可能性があります。
任意整理のメリット・デメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?」
個人再生
個人再生は裁判所に再生計画案を認めてもらうことで、借金を大幅に減額できる手続きです。100万円~5,000万円までの借金に有効で、借金総額に応じて次のような最低弁済額まで減額可能です。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 100万円以下 | 全額 |
| 100万円~500万円 | 100万円 |
| 500万円~1500万円 | 借金総額の1/5 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 借金総額の1/10 |
減額後の借金は、任意整理同様3年~5年かけて完済を目指します。そのため一定以上の安定した収入が必要に。原則としてすべての借金が対象となるので、保証人がいる借金がある場合には、減額分の返済義務が保証人に移ります。
また個人再生には、住宅ローンを返済し続けることで自宅を残せる「住宅ローン特則」があるのも特徴。自己破産のように借金理由を問題としないので、浪費やギャンブルが原因の人にも向いています。
個人再生のメリットとデメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」
自己破産
自己破産は借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらうことで、全ての借金返済義務を免除(免責)してもらえる手続き。借金をリセットできるので、返済に追われる日々から解放され、いち早く生活を再建できるのが大きなメリット。一方で自己破産には次のようなデメリットがあります。
- 一定以上の財産を処分される
- ブラックリストに載る
- 官報に公告される
- 資格や職業の制限がある
- 免責不許可事由がある
- 連帯保証人に返済義務が移る
自営業者の方の自己破産では、基本的に「管財事件」となるため次のようなデメリットが生じます。
- 破産管財人に支払う裁判所費用(予納金)が高額
- 郵便物が破産管財人に転送される
- 引っ越しや旅行が制限される
- 新たな借入ができない
- 事業継続が難しくなる
自己破産のデメリットについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」
弁護士に相談
債務整理を検討された方は、借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。法律に詳しくない人が自分で手続きしようと思っても、債権者との交渉や裁判所への手続きなどを失敗なく行うことは大変難しいと言わざるを得ません。また自分にどのような方法が合っているかも素人では判断できません。
しかし弁護士に債務整理の手続きを依頼することで、様々なメリットが受けられます。
- 債権者からの督促がストップできる
- 債務整理が終わるまで返済の必要がなくなる
- 自分にあった債務整理の方法をアドバイスしてもらえる
- 手続きに必要な書類の作成や収集を任せられる
- 債権者との交渉を任せられる
- 裁判所での手続きを任せられる
- 債務整理が成功しやすくなる
弁護士に依頼するにはある程度の費用がかかります。弁護士事務所によっては分割払いで対応可能なところもあるので、相談時に聞いてみましょう。また収入や資産が一定額以下の場合には、法テラスの「弁護士費用等の建て替え制度」などが利用できます。詳しくは法テラスのホームページをご参照ください。
自己破産は自分でできるのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産は自分でできる?手順と注意点、弁護士に依頼しないときのデメリットとは」
まとめ
住民税を滞納してしまうのは、「特別徴収」と「普通徴収」という2種類の徴収方法があるためです。住民票を滞納していると延滞税がかかり、督促状や差押予告通知書が届くようになります。実際に給与や預貯金が差し押さえられると、勤務先や取引先に税金を滞納していることがバレ、社会的信用がなくなってしまうでしょう。
滞納している住民税を支払えないときには役所の窓口に行き、減免申請や納税猶予申請ができないか相談してください。すでに差し押さえが目前に迫っている方は、換価の猶予申請や生活保護の申請が有効です。いくら支払えなくても時効を期待するのはナンセンスで、債務整理しても減免できない点に注意しましょう。
税金以外に借金がある方は、債務整理を検討した方がいいでしょう。借金の内容や原因、収入の有無など家計状況によって、最適な債務整理方法が異なります。まずは債務整理に詳しい弁護士に相談したうえで、効果的に借金を減免できる方法を見つけていきましょう。